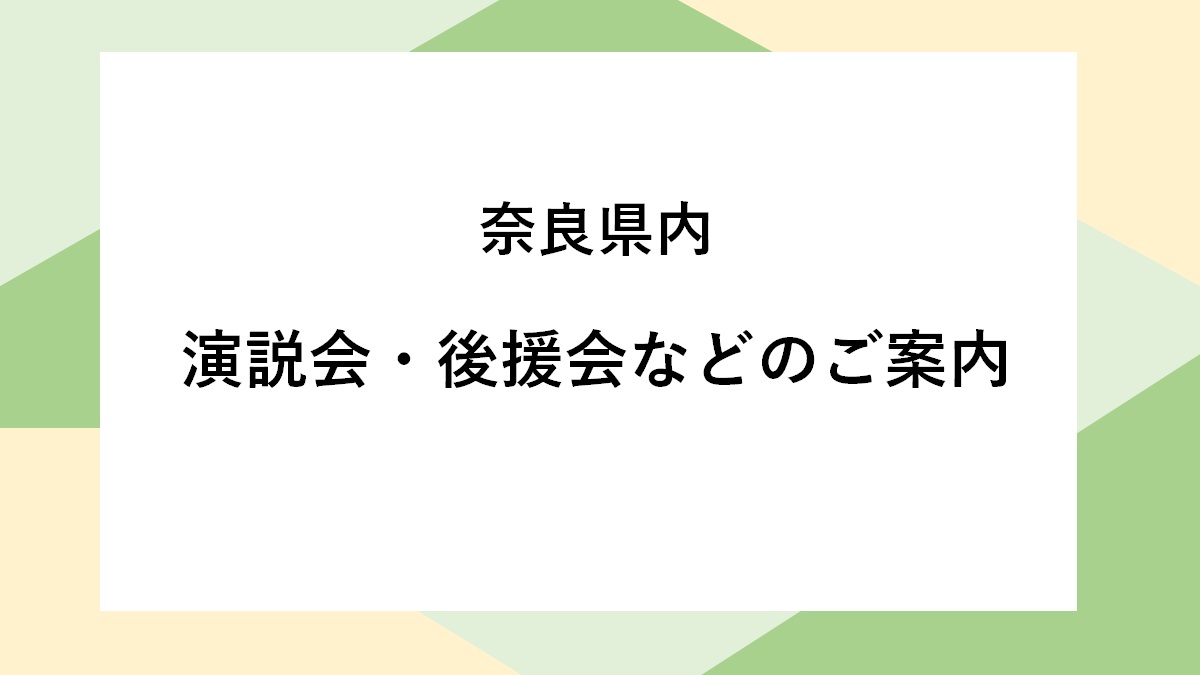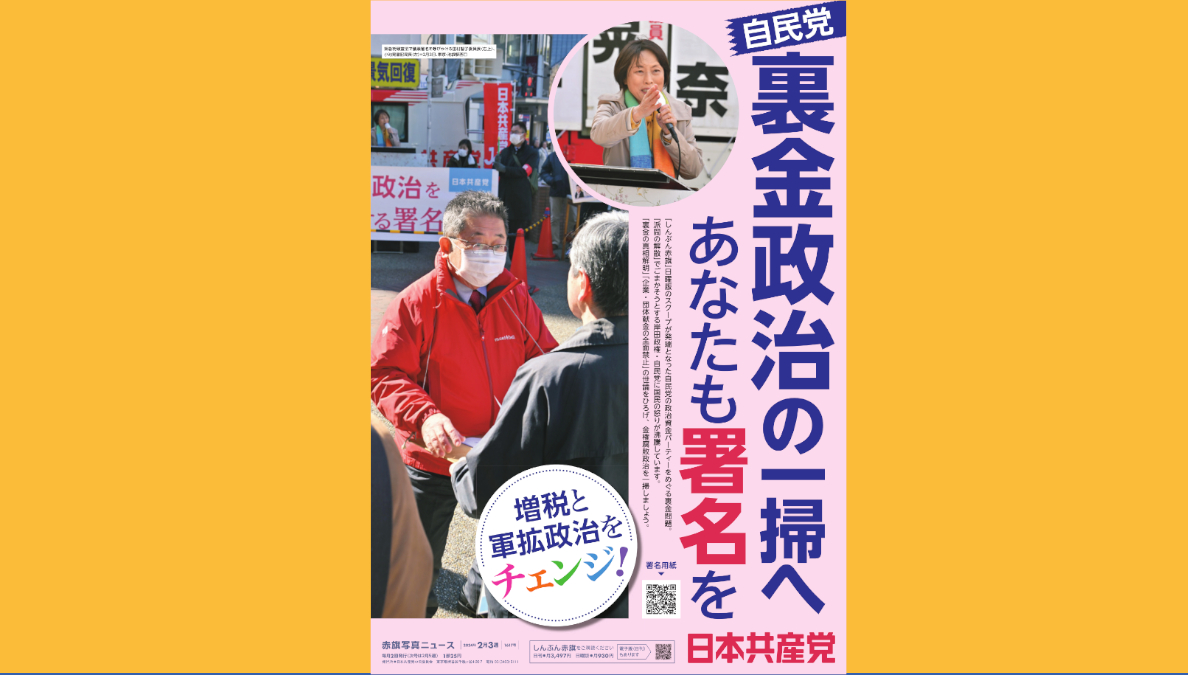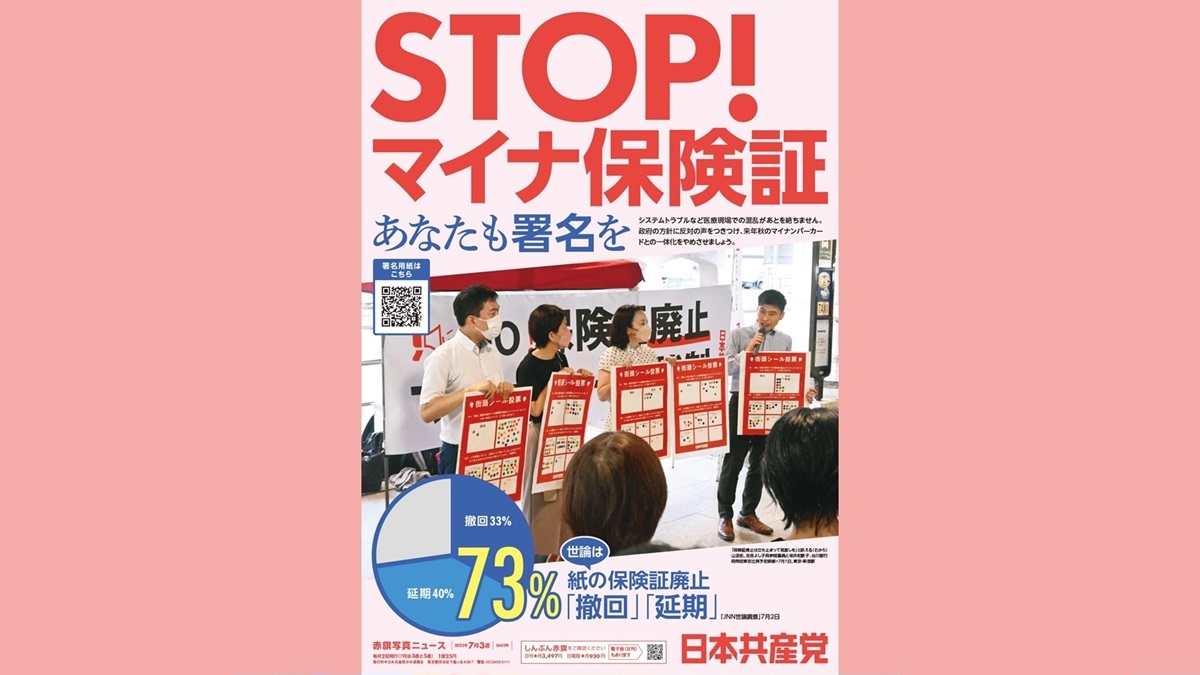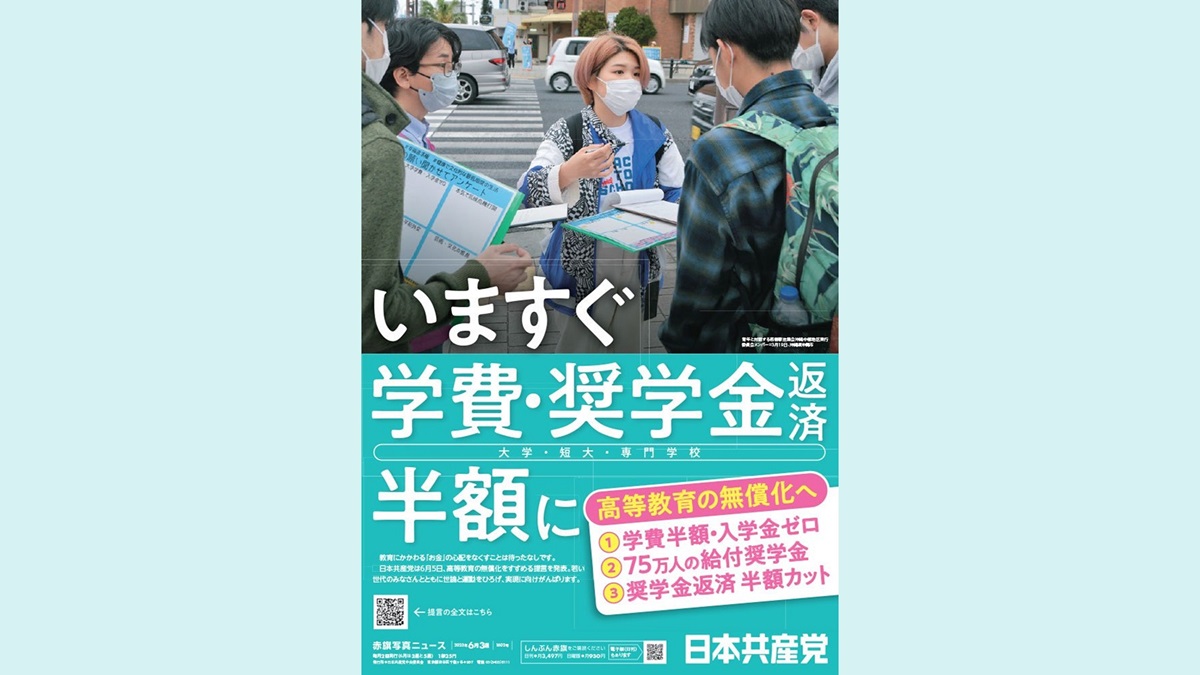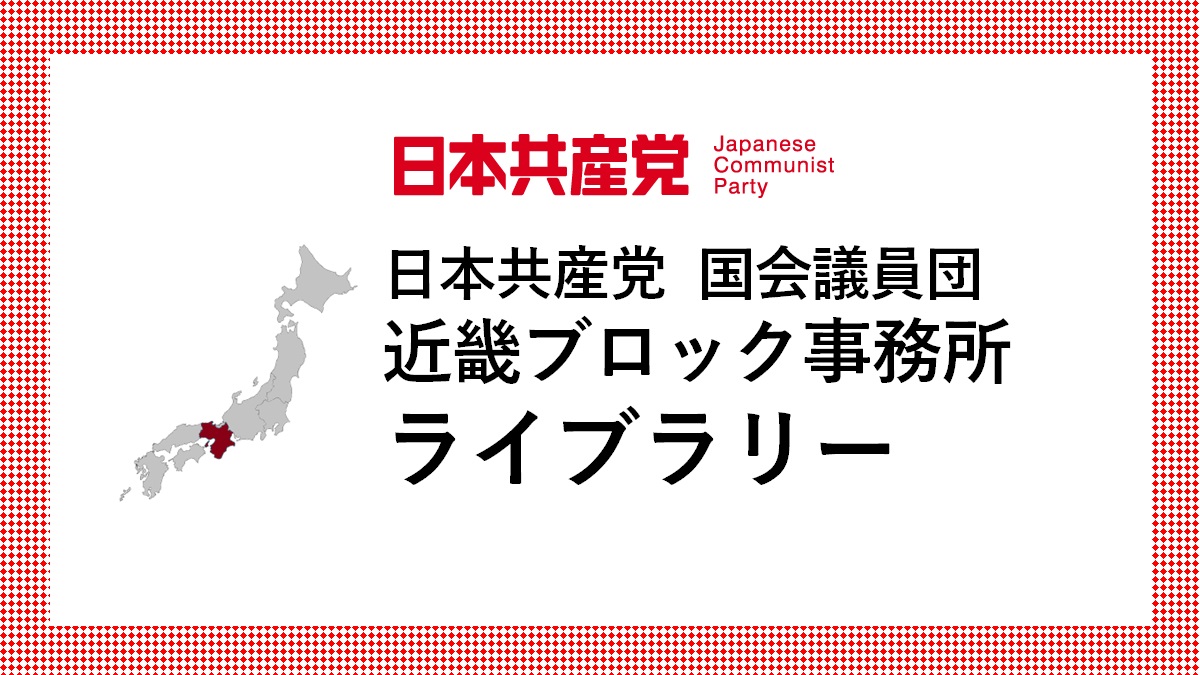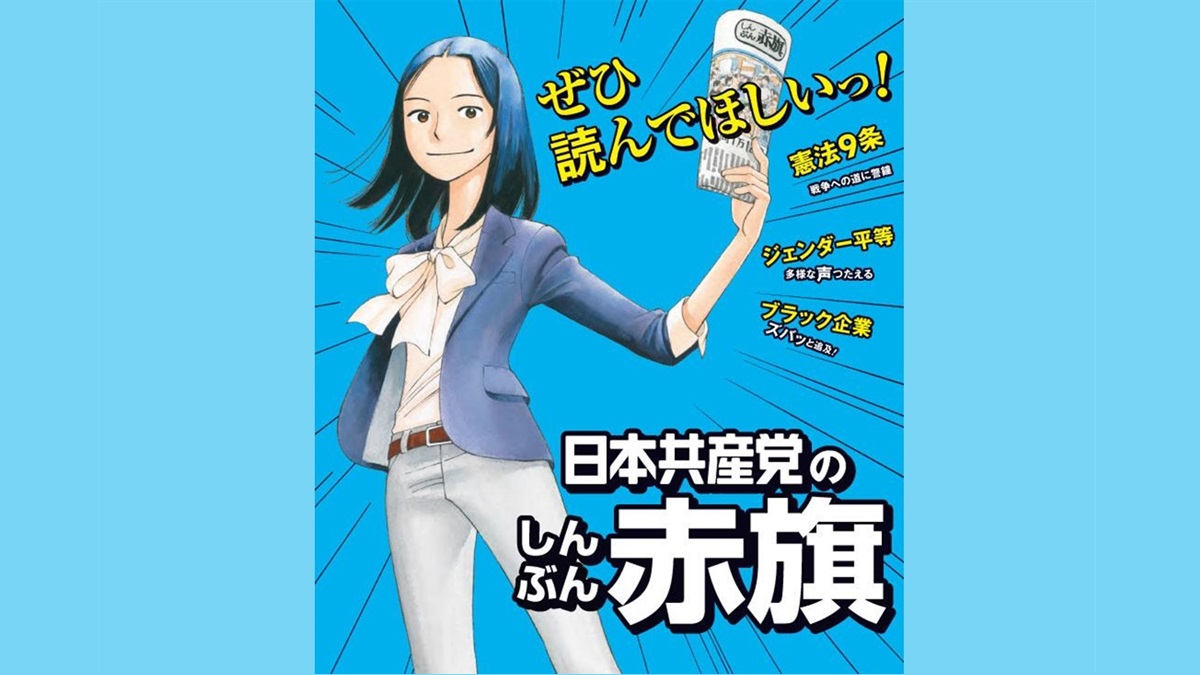奈良市は昨年(2003年)10月、(仮称)市立奈良病院の「基本構想」を発表しました。12月議会では「病院設置条例」が提出されました。
日本共産党は国立奈良病院の統廃合計画にいっかんして反対するとともに、統廃合決定後はその撤回を求めると同時に、公的医療の存続のために奈良市が移譲 をうけて国立奈良病院の存続をもとめる多くの市民のみなさんと共同してきました。奈良市が移譲をうけることを決定し、奈良市が国に「新病院基本構想」をま とめる時期である2003年1月、「奈良市立病院(仮称)の医療充実をもとめる私たちの提言(案)」を発表しました。「提言」は郵送や地域配布などもおこ ない、2月には幅広い方々の意見を聞くためにシンポジウムを開催してきました。昨年の提言の内容やこのかんのとりくみの経験もふまえ、奈良市立病院の開設 を歓迎し、さらに市民のためにその内容が充実されるよう、発表された「基本構想」へ問題提起をするものです。
1 医療内容について 公的病院として政策医療に重点を
(1)24時間小児救急の実施を 地域小児科センター病院をめざして
診療科目については、呼吸器科、消化器科などの診療科を加えるなど15診療科として、いっていの市民ニーズを反映したものといえますが、当初、市も言明 していた「24時間小児救急」は「病院輪番制に参加する」にとどまるなど、公的病院として果たすべき政策医療が明確でありません。
市民の要望の高い24時間の小児救急を実施するべきです。
「国立奈良病院の存続と地域医療を守る会」が奈良市が移譲を決定した後に実施されたアンケート(2002年秋)では「小児救急・小児科拡充」をもとめる声が14・8%とトップで子育て世代に限らず高齢者からも「少子化対策のために充実を」と多くよせられました。
奈良県保険医協会が昨年秋に実施された「小児救急を考えるアンケート」では回答した保護者のほとんどが時間外に子どもが急病になった経験をもち、「休日 夜間診療所」「病院」にあわせて8割の人が診察をうけたとこたえています。小児科標榜開業医も三分の一が小児の休日・夜間の緊急診療をおこなっており、小 児救急を「以前はおこなっていたが現在はしていない」開業医の理由は「体がもたない」「スタッフがいない」など深刻な実態があきらかになっています。二次 救急の受け入れ先をもとめる声も強いものがあります。一方、休日夜間診療所への協力を表明する小児科開業医もあり、関係者の協力をえて体制の強化も可能で はないでしょうか。NICUの不足も深刻です。
奈良県病院協会も、24時間小児救急、周産期医療、特科救急、休日夜間診療などの充実がもとめられていると要望されています。
日本小児科学会は「小児医療体制改革の目標と作業計画」の骨格をまとめましたが、30万人~50万人の規模で小児救急センター病院を提唱しています。奈良市立病院としても研究が必要ではないでしょうか。厚生労働省は、小児科医による夜間の電話相談を開始するとしていますが、診療を受け入れる体制がいっそ う重要となります。
こうした医療体制の整備を奈良市だけでおこなうことは無理で県との連携が必要です。1次救急は市町村が責任をおこなうものですが、2次救急は県の責任で おこなう分担になっています。実際の救急は奈良市以外の来院も一定の比率をしめると考えられます。こうした小児救急をNICUもふくめ、県の政策医療とし て奈良市立病院で実施することを県に強くもとめる必要があります。県立奈良病院との役割の分担の調整が必要と考えます。また、国にたいしても小児科医療制 度の拡充をもとめていくことも重要ではないでしょうか。
また、現在、医師会に委託し、医師会の献身的努力により対応している休日夜間応急診療所も半数以上を0歳から6歳の小児がしめている現状からも、将来的 には関係団体との合意をえて西部地域に休日夜間応急診療所を移設し1次救急体制の充実をはかることも検討します。市立病院が東部地域の休日夜間応急診療所 の機能もはたすとともに、全市的な1次、2次救急医療の中心的役割を担う体制づくりを検討します。
(2)救急医療体制の充実を。
第4次医療法の関係で昨年8月までに一般病床と療養病床の申請をおこなうことになっており、急性期に対応する病院の不足も懸念されます。奈良市立病院が 小児以外でも24時間いつでも安心してかかれる、救急医療体制を確立する必要があります。そのためにも、奈良医科大学の救命科からの医師の派遣など体制を 確立し、1次救急(外来診療のみで対応可能な比較的軽症の救急患者の診察を受け持つ)、2次救急の受け入れを積極的に行う体制づくりが必要です。市立病院 が1次・2次救急に積極的に対応できる受け皿をつくることで、県立奈良病院の3次救急・救命救急の効果をあげることになります。県に応分の負担をもとめ て、北和医療圏の救急告示病院・輪番病院のネットワークの軸となり、効率的な救急体制の確立をすすめることになるのではないでしょうか。
2 地域の医療機関との連携を重視して
(1)役割と機能の分担を
医師会や病院協会などとも意見交換を積極的におこない、奈良市に不足する医療について調査研究をする必要があります。奈良県の人口10万人あたりの病床数 は全国平均995人にたいして872、5人(2001年)と病床数は少なく、地域の後方支援病院としての役割は重要です。
これまで国立奈良病院が長年築き上げてきた開業医・中小民間病院とのネットワークを引き継ぎ、いっそうの機能分担と連携を強めることがもとめられています。
急性期入院加算の取得(紹介率30%、平均在院日数17日以内)なども研究するべきではないでしょうか。
(2)オープンシステムの研究
医師会の理解と協力を得て、市立であるという特徴を発揮したオープンシステム(開放型病院)の検討をします。オープンシステムはかかりつけ医の紹介で入 院しながら、かかりつけ医が市立病院にも赴いて市立病院の医師と協同で患者の治療をおこなう制度です。現在、奈良県では4病院が開放型病院として承認され ていますが、開業医との連携など、その機能が十分とはいえない状況にあります。地域医療連携室の設置、利用しやすいシステムづくり、連携ベッドの確保など も研究する必要があります。
(3)さらなる研究を
地域医療支援病院については、紹介率80%以上など条件を満たしていないことや、市民の市立病院との期待とのギャップも大きいことから、検討課題とする必要があります。また、ホスピス、緩和ケア病棟などについても、検討を要する課題ではないでしょうか。
3 市民とともに歩む市立病院を 何よりも市民参加をつらぬいて
積極的に情報公開と市民参加をつらぬくべきです。市民アンケートなど市民の意見を聞く場を設けるべきではないでしょうか。
「開設準備協議会」には公募をふくめて市民参加をつらぬき、会議は傍聴や会議録の公開を積極的におこない、会議内容を公開するべきです。
議会に特別委員会を設置するなど、特別の体制が必要です。横須賀市の市立うわまち病院は移譲を表明した翌年度から「病院問題特別委員会」を設置し、2年間にわたり集中審議をおこなっています。委員会の議事録はインターネットでも公開をされています。
市立病院の開設後も、「市立病院運営協議会」(仮称)を設置し、市立病院にふさわしい公的医療の継続、発展をはかることが必要です。協議会には有識者、市民代表などの参加をもとめ、開設後も市民参加で医療内容を発展させることが大切と考えます。
以上